はじめに|『真・鮫島事件』とは?

映画『真・鮫島事件』は、平成ネット史に刻まれた最大級の都市伝説「鮫島事件」を題材にしたホラー作品です。
2020年の公開以来、ネット文化や都市伝説に興味を持つ層から注目を集め、その独特な恐怖演出と題材選びで話題となりました。
オンライン会議アプリを舞台に、画面越しに迫り来る“呪い”が描かれ、現代的なシチュエーションと古典的な怪異が融合した一作です。
映画の概要と基本情報
- 公開年:2020年
- 監督・脚本:永江二朗
- 主演:武田玲奈(代表作:『人狼ゲーム インフェルノ』『踊ってミタ』)
- 配給:イオンエンターテイメント
- 上映時間:80分
- ジャンル:ホラー/都市伝説
物語は、高校時代の同級生たちがリモートで再会するオンライン会議から始まります。しかし、ある一人が姿を見せず、代わりに現れた人物から衝撃的な“死の告知”が…。そこから、かつてネット掲示板で広まった恐怖の都市伝説「鮫島事件」との関わりが明らかになっていきます。
元になった都市伝説「鮫島事件」とは何か
「鮫島事件」とは、2000年代初頭の巨大掲示板「2ちゃんねる」で生まれた、実体のない都市伝説です。
書き込みの中で「鮫島事件」の詳細を書こうとすると、必ず「それ以上は書くな、命が危ない」と制止される…というやり取りが定番化し、その“内容を誰も知らない”こと自体が恐怖と好奇心を煽りました。
真相不明のままネット上で語り継がれ、やがて「知った者は呪われる」という設定が加わり、平成ネット史の中でも特異な存在となっています。
映画『真・鮫島事件』は、この“語れない事件”を現代風に脚色し、映像化することで新たな恐怖体験として再構築しています。
本作は単なるホラー作品としてだけでなく、ネット文化と都市伝説の進化を知る上でも興味深い一作です。
あらすじ(ネタバレなし)|リモート会議から始まる恐怖
|リモート会議から始まる恐怖.jpg)
映画『真・鮫島事件』は、現代ならではのオンライン会議を舞台に、ネット発祥の都市伝説をモチーフに描かれたホラー作品です。ここでは結末や核心部分には触れず、物語序盤の流れをご紹介します。
高校の同級生たちの再会
高校時代の部活仲間である菜奈、裕貴、鈴、そしてあゆみは、毎年恒例となった同窓会をオンライン会議アプリで開催。画面越しに交わされる笑顔や思い出話からは、かつての友情が色濃く感じられます。
姿を見せないあゆみと“死の告知”
しかし、その日あゆみは画面に姿を現さず、代わりに接続したのは彼氏の匠。彼の口から語られたのは、あゆみが壮絶な表情のまま亡くなっていたという衝撃の知らせでした。仲間たちは言葉を失い、不安と恐怖に包まれます。
ネット掲示板から広まった呪いの存在
やがて話題は、20年前のネット掲示板「2ちゃんねる」で流行した“鮫島事件”という都市伝説に及びます。その真相に触れた者は必ず呪われる──そんな不気味な噂が、画面越しの空気を一変させていきます。
ネタバレあらすじ|呪いの真相と結末

ここから先は、映画『真・鮫島事件』の物語の核心部分に触れる内容となります。未鑑賞の方はご注意ください。
本作は都市伝説「鮫島事件」を題材に、呪いの発祥とその恐怖の連鎖を描いています。以下では、その真相と結末までの流れを詳しく紹介します。
廃墟での出来事
あゆみは仲間の裕貴、鈴と共に、「鮫島事件」の発祥地とされる廃墟を訪れます。そこは長年放置され、壁は剥がれ落ち、窓は割れ、風が通るたびに低く不気味な音を立てる場所でした。内部を探索する3人は、古びた机の上に残された不可解なメモや、壁に刻まれた奇妙な記号を発見します。その瞬間から、周囲の空気は一変し、背筋を冷やすような気配が漂い始めます。
あゆみの変化と不可解な現象
廃墟を訪れた後、あゆみは急に無口になり、どこか虚ろな表情を見せるようになります。同時に、彼女の周囲で説明のつかない現象が頻発。部屋の明かりが勝手に消える、スマホに意味不明な画像や音声が届く、そして誰もいないはずの場所から聞こえる足音…。仲間たちはその変化に不安を募らせます。
迫り来る“鮫島事件”の呪い
やがて呪いは、オンライン会議を通じて他の参加者にも及びます。画面越しに映るはずのない影や、人の顔がノイズ混じりに歪む映像が出現。さらに通話中、背後に立つ見知らぬ人物の姿が映り込み、恐怖は一気に頂点へと達します。
クライマックスの恐怖シーン
物語は、呪いの真相を探ろうとした菜奈たちが、逆にその核心に触れてしまう展開へ。廃墟とオンライン会議の映像が重なり、現実と虚構の境界が崩れ落ちます。最後に残されたのは、画面越しに突き付けられる“知ってはいけない真実”──そして、それを見た者の運命は誰一人として逃れられないことが示されます。
都市伝説「鮫島事件」のルーツとネット史

映画『真・鮫島事件』の元となった「鮫島事件」は、2000年代初頭の日本インターネット黎明期に誕生した都市伝説です。その発祥は巨大掲示板「2ちゃんねる」と言われ、今なおネット文化や都市伝説好きの間で語り継がれています。ここでは、その成り立ちと拡散経緯、そして他のネット発ホラーとの比較を紹介します。
2ちゃんねるでの発祥と拡散経緯
2000年代初頭、「2ちゃんねる」のスレッド内で突如として登場したのが“鮫島事件”という言葉です。スレッドの内容は一見すると日常的な雑談ですが、誰かが「鮫島事件って何?」と質問すると、すぐに「それ以上は言うな」「命が危ない」といった制止のレスが返されます。
このやり取りが繰り返されるうちに、あえて詳細を語らないことで逆に興味と恐怖を煽り、事件の知名度は急速に拡大していきました。
なぜ「真相を書けない」のか
鮫島事件の最大の特徴は、“詳細が一切語られない”という点です。具体的な内容が不明なまま、「知った者は必ず呪われる」「命を落とす」という設定だけが一人歩きしました。
この「空白」を残す構造こそが、都市伝説としての魅力を高め、ネット掲示板特有の遊び心と恐怖感を融合させることに成功しています。
他のネット発ホラーとの比較
鮫島事件は、「八尺様」や「くねくね」といったネット発の怪異譚と同じく、発祥時から多様な派生解釈や創作が生まれました。ただし、八尺様やくねくねは怪物や怪異の姿・行動がある程度描写されるのに対し、鮫島事件はその核心部分が完全に伏せられている点が異なります。
この“語られない恐怖”こそが、鮫島事件を平成ネット史の中でも特異な存在にしています。
映画と都市伝説の違い・脚色ポイント

『真・鮫島事件』は、ネット掲示板で語られてきた都市伝説をベースにしていますが、そのまま映像化しているわけではありません。実在する「鮫島事件」のネット上での成り立ちを踏まえつつ、映画ならではの演出や脚色が加えられています。ここでは、その違いと工夫のポイントを解説します。
廃墟の描写と映像化された恐怖
都市伝説に登場する「発祥の地」は具体的な場所や詳細が語られないのが特徴ですが、映画ではこれを架空の廃墟として具現化しています。
カメラワークや照明によって、剥がれ落ちた壁や割れた窓、長年放置された家具などの細部が強調され、視覚的な恐怖を増幅。観客がその場に居合わせているかのような臨場感を生み出しています。
実際の掲示板文化とのギャップ
現実の「2ちゃんねる」やネット掲示板では、文字だけのやり取りが中心で、恐怖は言葉の間や沈黙に生まれます。一方で映画は視覚と音声を使うため、その緊張感を再現するには別の工夫が必要です。
作中では、オンライン会議の映像越しに生じる違和感やノイズを利用し、テキストでは味わえない形で“見せる恐怖”を演出しています。
“ネットの闇”を映像化する難しさ
都市伝説の「鮫島事件」が持つ本質的な恐怖は、“詳細がわからないまま広がる噂”という構造にあります。しかし映像作品では、全く見せないままだと物語が成立しにくいため、ある程度の形を与える必要があります。
『真・鮫島事件』では、あえて核心をぼかしつつ、登場人物の反応や画面越しの異常現象を通じて“想像させる恐怖”を保ち続けています。
考察|『真・鮫島事件』が描く現代ホラーの本質

『真・鮫島事件』は、単なる都市伝説の映像化ではなく、現代社会における人々の恐怖感や不安心理を巧みに反映した作品です。本作の魅力は、オンライン会議という日常的な舞台設定と、不可視の恐怖を融合させた点にあります。ここでは、その本質に迫る3つの視点から考察します。
オンライン会議という舞台の必然性
オンライン会議は、コロナ禍以降の生活様式として広く普及しましたが、同時に「画面越し」という特異な距離感を生み出しました。
物理的には安全な場所にいながら、相手の背景や様子のすべてを把握できない――この不完全な情報環境が、ホラーの舞台として極めて効果的に作用しています。『真・鮫島事件』は、この現代的な状況を恐怖演出の中核に据えています。
「見えない恐怖」と心理的圧迫感
本作では、幽霊や怪異をはっきり映さず、画面の端や通信の乱れといった間接的な手段で存在を示します。この「見えない恐怖」は、観客の想像力を刺激し、視覚に依存しない深い不安感を呼び起こします。
また、オンライン会議の画面は四角い枠に人物を閉じ込めるため、視覚的にも圧迫感を与え、逃げ場のない心理状態を強調します。
呪いと情報拡散の共通点
呪いが人から人へと広がっていく様子は、SNSやネット掲示板における情報の拡散に酷似しています。
鮫島事件のように「詳細が不明なまま恐怖だけが拡散する」現象は、現代のデマや都市伝説の広がり方と共鳴し、観客にリアリティのある恐怖を与えます。
本作は、この現象を物語構造に組み込み、ネット社会特有の恐怖と呪いを重ね合わせることで独自の恐怖体験を作り出しています。
感想・評価|見どころと惜しいポイント

映画『真・鮫島事件』は、都市伝説を題材にしつつ現代的な恐怖を描いたホラー作品です。ここでは、作品を鑑賞して感じた見どころと、惜しいと感じたポイントを整理します。
ホラー演出の魅力
本作の最大の魅力は、直接的な恐怖描写を控え、間接的な演出でじわじわと不安を煽るスタイルにあります。
画面の端に映る影、通信の乱れによる映像ノイズ、聞き取りにくい音声など、観客の想像力を刺激する要素が巧みに配置されています。これにより、派手さはないものの、鑑賞後もしばらく余韻が残る恐怖感を実現しています。
キャストの演技力
主演の武田玲奈をはじめ、登場人物たちの演技がリアルで説得力があります。特にオンライン会議中の自然な会話や、徐々に恐怖に侵食されていく表情の変化は見事で、観客を物語に引き込みます。
また、緊迫感を保ちながらも自然体の演技を続けることで、作品全体にリアリティを与えています。
映像・音響の印象
映像は全体的に暗めのトーンで統一され、廃墟や夜のシーンでは特に不穏な雰囲気が際立ちます。音響面では、環境音やわずかなノイズが効果的に使われており、静寂と突然の音の対比が緊張感を高めています。
ただし、恐怖演出を控えめにしている分、ホラー映画としてのインパクトを求める観客にはやや物足りなく感じられるかもしれません。
『鮫島事件』関連作品&おすすめホラー映画

映画『真・鮫島事件』をきっかけに、ネット系ホラーや都市伝説を題材にした映画に興味を持った方も多いはずです。ここでは、本作と合わせて観ることで世界観が広がるネット系ホラー作品や、同じく都市伝説をモチーフにしたおすすめ映画を紹介します。
「真・鮫島事件」と合わせて観たいネット系ホラー
『真・鮫島事件』はオンライン会議を舞台にした現代的ホラーですが、ネットやSNSを題材にした作品は他にも存在します。
- #生きている(韓国) SNSとスマホを駆使し、ゾンビパンデミックを生き延びようとする若者のサバイバルホラー。閉鎖的な環境とオンライン要素が『真・鮫島事件』と共通。
- カメラを止めるな!スピンオフ短編 映像制作の舞台裏を描きつつ、オンラインを通じたやり取りや映像トラブルをユーモラスかつスリリングに表現。
- アンフレンデッド(海外) ビデオチャット画面のみで進行するサスペンスホラー。オンライン画面を活用した恐怖演出は必見。
他の都市伝説系映画
『鮫島事件』のように、日本の都市伝説を題材にしたホラー映画も数多く制作されています。以下の作品は、同じく実在の噂や怪異譚を元にしたストーリーが魅力です。
- 口裂け女 1970年代から日本各地で噂された怪人を題材にした作品。昭和の怪談ブームを知る上でも興味深い一作。
- 残穢【ざんえ】 -住んではいけない部屋- 実話怪談をベースに、不気味な部屋の過去と連鎖する怪異を描く。取材型の進行がリアリティを高めています。
- 八尺様(短編映画・オムニバス収録作) ネット掲示板で人気を集めた怪異譚を映像化。独特の間とビジュアルで“語られる恐怖”を形にしています。
まとめ|『真・鮫島事件』が残した恐怖とネット文化の影

『真・鮫島事件』は、平成ネット史上最大級の都市伝説をベースに、現代的な恐怖と社会背景を織り交ぜたホラー映画です。オンライン会議という日常的なツールを舞台にしながら、観客に「見えないもの」への恐怖と、情報が拡散していく現代社会の危うさを突き付けました。ここでは、本作の持つ意義と、ホラー映画ファンへのメッセージを整理します。
都市伝説を題材にした意義
鮫島事件という“詳細不明の噂”をあえて題材にすることで、作品は想像力を刺激し、観客自身に物語の空白を埋めさせる構造を持たせています。
この「語られない部分が恐怖を増幅させる」手法は、都市伝説が長く語り継がれる理由そのものであり、ネット文化がもたらした新しいホラーの形と言えます。
また、実際の掲示板文化を下敷きにすることで、リアリティとフィクションが交錯し、物語の没入感を高めています。
ホラー映画好きへのメッセージ
『真・鮫島事件』は、派手なジャンプスケアやグロテスク描写よりも、静かに忍び寄る不安感を重視した作品です。そのため、じわじわと迫る恐怖や心理的緊張感を好むホラーファンにとっては特におすすめです。
また、ネットやSNS、都市伝説といった現代的な題材に興味がある人にとっては、単なる娯楽映画を超えて、ネット社会に潜む“見えない危険”を考えるきっかけになるでしょう。
















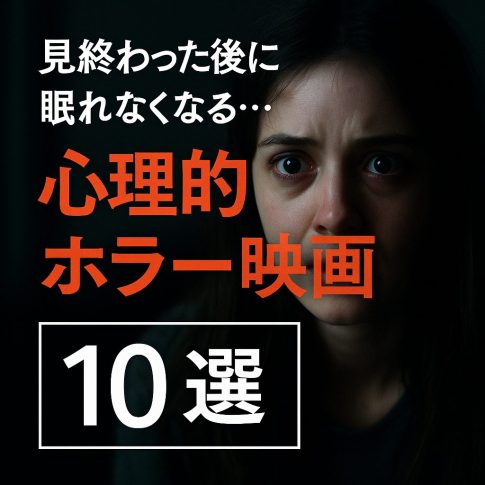


本記事で使用している作品に関する文章・画像は、映画『真・鮫島事件』および関連資料に基づき、引用の範囲内で掲載しています。引用部分の著作権は各権利者に帰属します。引用箇所には出典を明記し、批評・解説を目的として使用しています(著作権法第32条に基づく引用)。
また、一部の画像はAIツール(OpenAI「DALL·E」等)を用いて生成しています。AI生成画像は作品の公式素材ではなく、本記事用に独自作成したイメージです。記事内のテキスト・画像・構成の無断転載・無断使用を固く禁じます。